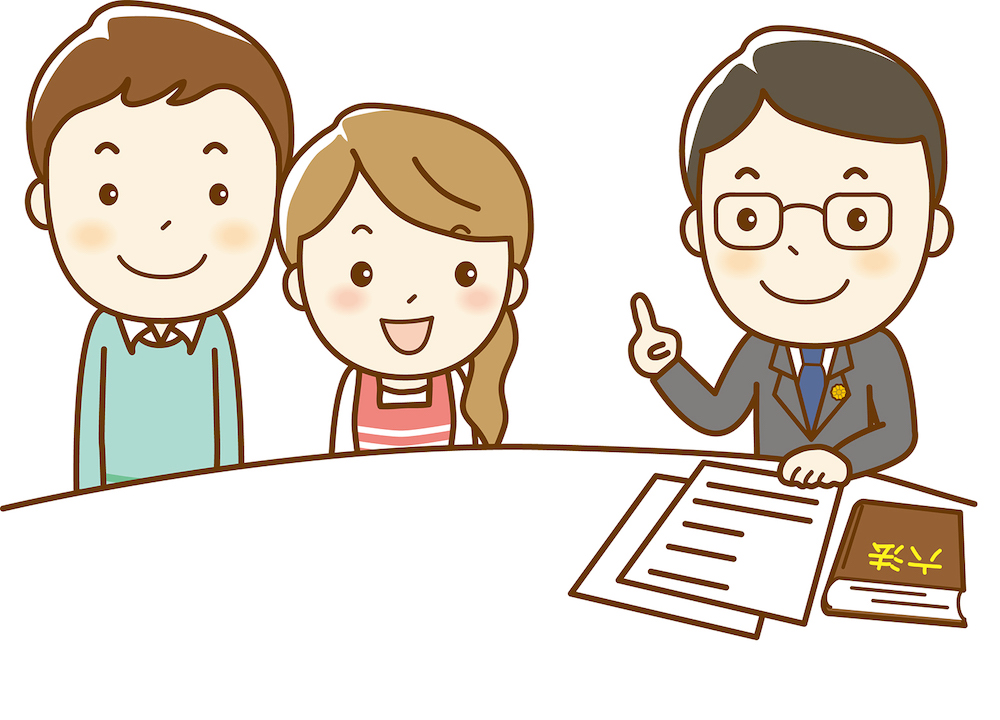顧問弁護士は個人や企業、団体と契約を結ぶことでいろいろな問題について相談にのり、法律上の視点からその解決方法をアドバイスする弁護士のことです。
継続的に契約することで、いつでもすぐに相談にのることができ、持続的に問題解決に向けてアドバイスをしてくれます。
一般的に弁護士に相談するとなると、まず弁護士を探すことから始め、次に内容を伝え、対応してもらえるかどうかを確認し、費用や日程を決めてから相談という流れになりますが、顧問弁護士だと一定期間契約することで、問題が生じた場合はすぐに電話で相談することができ対応してもらえます。
また、継続契約していることで会社の内部事情や事業状況もしっかり把握しているので、依頼主の視点から問題解決に向けて対処することができます。
参考>>大阪で評判の良い顧問弁護士事務所
顧問弁護士の主な仕事は日常の法律相談や各種契約書の確認、内容証明郵便等の作成ですが、この他にも訴訟が生じた場合の対応や社内体制の構築、社内の法律が関わってくる仕事など、幅広い分野に及びます。
契約するメリットとしては、企業間のM&Aなどをおこなう場合、相手先の調査や情報収集を自分でする必要がなく任せることができる、トラブルが発生した場合も法律的にどう関係してくるかを電話で相談するだけで回答が得られ、取るべき行動が教えてもらえ、相手方とも交渉してもらえるなど、短時間で問題解決ができることです。
また紛争の原因となりやすい契約書の作成も、文面や言葉をチェックしてもらうことができるので、問題発生のリスクを軽減でき、万が一トラブルが生じた場合でも相手側の弁護士とプロどうしで交渉してもらえるのでスムーズな問題解決につながります。
弁護士というと問題や紛争が起きたときに解決してくれるという印象が強いかもしれませんが、問題を未然に防ぐのも仕事です。
顧問弁護士は会社の内部事情や特徴を把握しているため、新規事業立ち上げや新たな商品やサービスの提供に際して、事前に打ち合わせをすることでリスクになりそうな問題を予め察知し、防止するためのアドバイスと手段を提示することができます。
企業によっては法律専門の部署を置いて詳しい従業員を雇う会社もありますが、いつも問題が起きるとは限らないので、そのためだけに雇用するのは人件費の無駄になります。
それに実際に問題が起きたときにその従業員が内容を把握し、分析し、改めて相談できる弁護士を探すよりも、契約弁護士の方が短時間で確実に問題に対処できます。
弁護士と顧問契約を結ぶことの利点について説明してきましたが、重要なことは依頼企業との間に高い信頼性が構築された上で問題を解決できるということです。
問題や紛争の種類によっては解決までに長くかかることもあり、その間に事業運営や社内の状況も変化することもありますが、そのような中にあっても企業と弁護士の信頼関係が構築できていれば、それを前提にお互い協力しながら問題解決に向けて動くことができます。
またそうすることで時間や費用だけでなく、紛争中でも経営者は安心して事業に専念することができます。
このようにいろいろなメリットが考えられる顧問弁護士ですが、契約するには費用がかかります。
相談や問題処理の有る無しに関係なく固定費用がかかってくるため、無駄なのではと考える人もいるかもしれませんが、契約内容によっては民事事件だけでなく、従業員が起こした刑事事件が含まれることもあるので、いざトラブルが起きたときに素人が対応するよりも法律のプロが解決に向けて動いた方が企業側も安心なはずです。
顧問料は弁護士によって異なりますし、中には比較的リーズナブルな価格で顧問を引き受けてくれるところもあるので、万が一のときの保険に入るような感覚で顧問契約するのも良いのかもしれません。
顧問弁護士の探し方ですが、問題が起きたときに誰が対処するかによって結果が大きく違ってくることもあるので慎重になる必要があります。
インターネットを使ってマッチングするのも一つですが、親しくしている企業の経営者や、自社の税理士、社労士に相談してみるという方法もあります。
どんな分野に強い弁護士を選ぶかにもよりますが、自社の税理士や労務士ならば会社のことをよく分かっていますし、同じ士業つながりから専門分野で協力して業務を進めていることも多いので、信頼度が増すだけでなく会社にあった人を紹介してもらえる可能性が高くなります。
日本弁護士連合会に相談するのも一つです。
弁護士は全員、加盟しており、企業の世界進出によって海外企業との折衝もあるため外国人弁護士も特別会員として登録されています。
また加盟している弁護士に対して指導、監督に関わる事務をおこない、会則などを制定しているので信頼できると言えます。
紹介してもらったら契約する前に法律相談をしたり、具体的な案件を依頼して仕事ぶりを見るというのも一つです。
仕事の進め方でどのような考えの持ち主か検討がつきますし、自社との相性も確認できます。
最終更新日 2025年6月9日