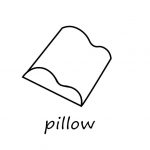景品表示法に基づき、それに違反する事業者などに対し、消費者庁は措置命令を出すことができます。
ただ、いきなり措置命令を出すのではなく、いくつかのプロセス、段階があります。
最初に一般の消費者、もしくは事業者からの通報などで景品表示法に反することをしている事業者の存在が明らかになります。
その行為が景品表示法に違反しているのかどうか、もしくは業界で自主的に定められているルールに反しているのかどうかを確認する作業に入ります。
そして、当事者などに弁明の機会を与えることになります。
弁明の機会というのは面談だけに限らず、書面による弁明や証拠の提出といったものとなっており、その期間に弁明や証拠の提出を一切しない事業者も中には存在します。
しかしながら、弁明の機会を与えた段階で多くの事業者は景品表示法に違反していることを重く受け止め、現在行われている表示を改善するようになります。
措置命令が出るまで景品表示法に明らかに違反した表示を続け、命令が出てから止めるというやり方は消費者の信頼を一気に失うだけでなく、企業イメージに大きな影響を与える行為といえます。
そのため、調査が入った時点で違反状態をやめ、命令が出た段階ではすでに改善されているケースが多く、報道などで発表がなされた時点では、もう改善に取り組んでいますと終わったことのように扱う企業がほとんどです。
中には措置命令に納得がいかないところもありますが、その命令に不服申し立てを行う事業者はほぼない状況です。
措置命令の件数は一時的に増加した時期はあったものの、基本的には同じような件数で推移しています。
また、措置命令を出しても改善されないケースはほとんどなく、多くの場合は改善する、もしくは商品の取り扱い自体やめるといったところがあります。
こうした措置命令は消費者庁に限らず、都道府県でも行うことができます。
あくまで違反行為を迅速に取り締まるために、都道府県にもこうした権限が与えられているのです。
最終更新日 2025年6月9日